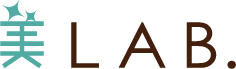ヨーグルトを味方につける!腸内環境UPの秘策★
役割と日本での歴史
乳酸菌が多く含まれるヨーグルトは大腸内を酸性に保ち、善玉菌の代表・ビフィズス菌の働きを助け、悪玉菌の繁殖を抑制してくれる役割があります。
その歴史は古く、紀元前3000年とも言われています。しかし、ヨーグルト(加糖タイプ)が私たち日本人の口に入るようになったのは、つい100年ほど前。プレーン(無糖タイプ)のヨーグルトに至っては半世紀も経過していないニューウェーブです。昨今の健康志向が追い風となり、トクホ(特定保健用食品)がついたもの、機能性を重視したものなどその種類もずいぶん増え、スーパーやコンビニなどで当たり前のように手に入るようになりました。
ヨーグルトならなんでもいいの?
手軽に食べられるヨーグルトですが、商品ごとに乳酸菌の種類が違うと言っても言い過ぎではありません。種類が違うイコール期待される効果・効能が違います。そのため、ヨーグルトを食べることが大事というより、じぶんの腸に合ったヨーグルトを見極めて食べることが大事になってきます。

相性チェックのやり方
ヨーグルトとじぶんの腸との相性を確かめる方法は、実践あるのみ!その方法は短くても3~4日、できれば1週間程度食べ続けてみることです。1日の摂取量の目安は200~250グラムほど。1回で食べても2~3回に分けても構いません。食べ続けている期間で、じぶんの腸内細菌たちとうまくやっていけそうか様子を見ます。
相性がいいと臭くないオナラが出るようになったり、便の色や形、量に変化が出てきます。変化がほとんど感じられない場合はさっさと次の相手(ヨーグルト)に乗りかえましょう。

せっかく食べるのですから、じぶんの腸に合ったものを!次回はヨーグルトに●●をちょい足ししてバリエーション豊かになるアレンジ術をご紹介します。
- 執筆者:
- 真野 わか